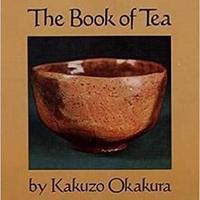第一章 人情の碗
だい ひと しょう|にんじょう の わん
茶 は 薬用 と して 始まり 後 飲料 と なる 。
ちゃ||やくよう|||はじまり|あと|いんりょう||
Tea begins as a medicinal product and then becomes a beverage.
シナ に おいて は 八 世紀 に 高 雅 な 遊び の 一 つ と して 詩歌 の 域 に 達した 。
しな||||やっ|せいき||たか|ただし||あそび||ひと||||しいか||いき||たっした
In China, it reached the level of poetry as one of the noble play in the 8th century.
十五 世紀 に 至り 日本 は これ を 高めて 一種 の 審 美的 宗教 、 すなわち 茶道 に まで 進めた 。
じゅうご|せいき||いたり|にっぽん||||たかめて|いっしゅ||しん|びてき|しゅうきょう||さどう|||すすめた
In the fifteenth century, Japan raised this to a kind of aesthetic religion, the tea ceremony.
茶道 は 日常 生活 の 俗 事 の 中 に 存 する 美しき もの を 崇拝 する こと に 基づく 一種 の 儀式 であって 、 純粋 と 調和 、 相互 愛 の 神秘 、 社会 秩序 の ローマン 主義 を 諄々 と 教える もの である 。
さどう||にちじょう|せいかつ||ぞく|こと||なか||ぞん||うつくしき|||すうはい||||もとづく|いっしゅ||ぎしき||じゅんすい||ちょうわ|そうご|あい||しんぴ|しゃかい|ちつじょ|||しゅぎ||じゅんじゅん||おしえる||
The tea ceremony is a kind of ritual based on worshiping the beautiful things that exist in the profane of daily life, and teaches pure and harmony, the mystery of mutual love, and the romanticism of social order.
茶道 の 要 義 は 「 不完全な もの 」 を 崇拝 する に ある 。
さどう||かなめ|ただし||ふかんぜんな|||すうはい|||
いわゆる 人生 と いう この 不可解な もの の うち に 、 何 か 可能な もの を 成就 しよう と する やさしい 企て である から 。
|じんせい||||ふかかいな|||||なん||かのうな|||じょうじゅ|||||くわだて||
Because it is a gentle attempt to achieve something possible in this mysterious so-called life.
茶 の 原理 は 普通の 意味 で いう 単なる 審 美 主義 で は ない 。
ちゃ||げんり||ふつうの|いみ|||たんなる|しん|び|しゅぎ|||
The principle of tea is not just aestheticism in the ordinary sense.
と いう の は 、 倫理 、 宗教 と 合して 、 天人 に 関する われわれ の いっさい の 見解 を 表わして いる もの である から 。
||||りんり|しゅうきょう||あわして|てんにん||かんする|||||けんかい||あらわして||||
Because, together with ethics and religion, it represents all of our views on heavenly people.
それ は 衛生 学 である 、 清潔 を きびしく 説く から 。
||えいせい|まな||せいけつ|||とく|
It's hygiene, because it rigorously preaches cleanliness.
それ は 経済 学 である 、 と いう の は 、 複雑な ぜいたく と いう より も むしろ 単純 の うち に 慰安 を 教える から 。
||けいざい|まな||||||ふくざつな|||||||たんじゅん||||いあん||おしえる|
それ は 精神 幾何学 である 、 なんとなれば 、 宇宙 に 対する われわれ の 比例 感 を 定義 する から 。
||せいしん|きかがく|||うちゅう||たいする|||ひれい|かん||ていぎ||
It is mental geometry, because it defines our sense of proportion to the universe.
それ は あらゆる この 道 の 信者 を 趣味 上 の 貴族 に して 、 東洋 民主 主義 の 真 精神 を 表わして いる 。
||||どう||しんじゃ||しゅみ|うえ||きぞく|||とうよう|みんしゅ|しゅぎ||まこと|せいしん||あらわして|
It represents the true spirit of oriental democracy, making every believer on this path a hobbyist aristocrat.
日本 が 長い 間 世界 から 孤立 して いた の は 、 自省 を する 一助 と なって 茶道 の 発達 に 非常に 好都合であった 。
にっぽん||ながい|あいだ|せかい||こりつ|||||じせい|||いちじょ|||さどう||はったつ||ひじょうに|こうつごうであった
Japan's long isolation from the world helped to reflect on itself and was very favorable to the development of the tea ceremony.
われら の 住居 、 習慣 、 衣食 、 陶 漆器 、 絵画 等 ―― 文学 で さえ も ―― すべて その 影響 を こうむって いる 。
||じゅうきょ|しゅうかん|いしょく|とう|しっき|かいが|とう|ぶんがく||||||えいきょう|||
Our dwellings, customs, clothing, food, ceramics, lacquer ware, paintings, etc.-even literature-are all affected.
いやしくも 日本 の 文化 を 研究 せんと する 者 は 、 この 影響 の 存在 を 無視 する こと は でき ない 。
|にっぽん||ぶんか||けんきゅう|||もの|||えいきょう||そんざい||むし|||||
Anyone who is willing to study Japanese culture cannot ignore the existence of this effect.
茶道 の 影響 は 貴 人 の 優雅な 閨房 に も 、 下 賤 の 者 の 住み 家 に も 行き渡って きた 。
さどう||えいきょう||とうと|じん||ゆうがな|けいぼう|||した|せん||もの||すみ|いえ|||ゆきわたって|
The influence of the tea ceremony has spread to your graceful lounge and to the dwellings of the lower servants.
わが 田 夫 は 花 を 生ける こと を 知り 、 わが 野 人 も 山水 を 愛でる に 至った 。
|た|おっと||か||いける|||しり||の|じん||さんすい||めでる||いたった
My husband learned that flowers can grow, and my wilderness came to love Sansui.
俗に 「 あの 男 は 茶 気 が ない 」 と いう 。
ぞくに||おとこ||ちゃ|き||||
It is commonly said that "that man has no tea".
もし 人 が 、 わが 身の上 に おこる まじめ ながら の 滑稽 を 知ら ない ならば 。
|じん|||みのうえ||||||こっけい||しら||
If one does not know the serious humor that occurs on me.
また 浮世 の 悲劇 に とんじゃく も なく 、 浮かれ 気分 で 騒ぐ 半 可 通 を 「 あまり 茶 気 が あり 過ぎる 」 と 言って 非難 する 。
|うきよ||ひげき|||||うかれ|きぶん||さわぐ|はん|か|つう|||ちゃ|き|||すぎる||いって|ひなん|
In addition, he criticizes half of the tragedy of the Ukiyo, saying that he is "too much tea" and makes a noise with a feeling of floating.
よそ の 目 に は 、 つまら ぬ こと を このように 騒ぎ立てる の が 、 実に 不思議に 思わ れる かも しれ ぬ 。
||め||||||||さわぎたてる|||じつに|ふしぎに|おもわ||||
To the other eye, it may seem strange to make such a fuss about boring things.
一 杯 の お茶 で なんという 騒ぎ だろう と いう であろう が 、 考えて みれば 、 煎 ずる ところ 人間 享 楽 の 茶碗 は 、 いかにも 狭い もの で は ない か 、 いかにも 早く 涙 で あふれる で は ない か 、 無 辺 を 求 む る 渇 の とまら ぬ あまり 、 一息 に 飲みほさ れる で は ない か 。
ひと|さかずき||おちゃ|||さわぎ||||||かんがえて||い|||にんげん|あきら|がく||ちゃわん|||せまい|||||||はやく|なみだ|||||||む|ほとり||もとむ|||かわ|||||ひといき||のみほさ|||||
What a fuss about a cup of tea, but when you think about it, the teacups for human enjoyment, where they are brewed, are not so narrow, and aren't they overflowing with tears very quickly? Isn't the thirst for nothingness so much that you can drink it in one breath?
して みれば 、 茶碗 を いくら もてはやした とて とがめ だてに は 及ぶ まい 。
||ちゃわん||||||||およぶ|
Then, no matter how much the bowl was touted, it wouldn't be a blame.
人間 は これ より も まだまだ 悪い こと を した 。
にんげん||||||わるい|||
Humans have done something worse than this.
酒 の 神 バッカス を 崇拝 する の あまり 、 惜し げ も なく 奉納 を し 過ぎた 。
さけ||かみ|||すうはい||||おし||||ほうのう|||すぎた
He worshiped Bacchus, the god of liquor, and devoted himself too much.
軍 神 マーズ の 血なまぐさい 姿 を さえ も 理想 化 した 。
ぐん|かみ|||ちなまぐさい|すがた||||りそう|か|
Even the bloody appearance of the army god Mars has been idealized.
して みれば 、 カメリヤ の 女 皇 に 身 を ささげ 、 その 祭壇 から 流れ出る 暖かい 同情 の 流れ を 、 心 ゆく ばかり 楽しんで も よい で は ない か 。
||||おんな|こう||み||||さいだん||ながれでる|あたたかい|どうじょう||ながれ||こころ|||たのしんで||||||
Then, why not dedicate yourself to the Empress of Camellia and enjoy the warm flow of sympathy that flows from the altar to your heart's content?
象牙 色 の 磁器 に もられた 液体 琥珀 の 中 に 、 その道 の 心得 ある 人 は 、 孔子 の 心 よき 沈黙 、 老 子 の 奇 警 、 釈迦 牟尼 の 天上 の 香 に さえ 触れる こと が できる 。
ぞうげ|いろ||じき||もら れた|えきたい|こはく||なか||そのみち||こころえ||じん||こうし||こころ||ちんもく|ろう|こ||き|けい|しゃか|むあま||てんじょう||かおり|||ふれる|||
In the liquid amber in ivory-colored porcelain, those who know the way can touch the confucius's heart-warming silence, the old child's miracle, and even the heavenly incense of Buddha.
おのれ に 存 する 偉大なる もの の 小 を 感ずる こと の でき ない 人 は 、 他人 に 存 する 小 なる もの の 偉大 を 見のがし がちである 。
||ぞん||いだいなる|||しょう||かんずる|||||じん||たにん||ぞん||しょう||||いだい||みのがし|
一般 の 西洋 人 は 、 茶の湯 を 見て 、 東洋 の 珍 奇 、 稚気 を なして いる 千百 の 奇 癖 の また の 例 に 過ぎ ない と 思って 、 袖 の 下 で 笑って いる であろう 。
いっぱん||せいよう|じん||ちゃのゆ||みて|とうよう||ちん|き|ちき||||せんひゃく||き|くせ||||れい||すぎ|||おもって|そで||した||わらって||
西洋 人 は 、 日本 が 平和な 文芸 に ふけって いた 間 は 、 野蛮 国 と 見なして いた もの である 。
せいよう|じん||にっぽん||へいわな|ぶんげい||ふけ って||あいだ||やばん|くに||みなして|||
しかる に 満州 の 戦場 に 大々的 殺戮 を 行ない 始めて から 文明 国 と 呼んで いる 。
||まんしゅう||せんじょう||だいだいてき|さつりく||おこない|はじめて||ぶんめい|くに||よんで|
近ごろ 武士 道 ―― わが 兵士 に 喜び勇んで 身 を 捨て させる 死 の 術 ―― に ついて 盛んに 論評 されて きた 。
ちかごろ|ぶし|どう||へいし||よろこびいさんで|み||すて|さ せる|し||じゅつ|||さかんに|ろんぴょう|さ れて|
しかし 茶道 に は ほとんど 注意 が ひかれて いない 。
|さどう||||ちゅうい||ひか れて|
この 道 は わが 生 の 術 を 多く 説いて いる もの である が 。
|どう|||せい||じゅつ||おおく|といて||||
もし われわれ が 文明 国 たる ため に は 、 血なまぐさい 戦争 の 名誉に よら なければ なら ない と する ならば 、 むしろ いつまでも 野蛮 国 に 甘んじよう 。
|||ぶんめい|くに|||||ちなまぐさい|せんそう||めいよに||||||||||やばん|くに||あまんじよう
われわれ は わが 芸術 および 理想 に 対して 、 しかるべき 尊敬 が 払わ れる 時期 が 来る の を 喜んで 待とう 。
|||げいじゅつ||りそう||たいして||そんけい||はらわ||じき||くる|||よろこんで|まとう
いつ に なったら 西洋 が 東洋 を 了解 する であろう 、 否 、 了解 しよう と 努める であろう 。
|||せいよう||とうよう||りょうかい|||いな|りょうかい|||つとめる|
われわれ アジア 人 は われわれ に 関して 織り 出さ れた 事実 や 想像 の 妙な 話 に しばしば 胆 を 冷やす こと が ある 。
|あじあ|じん||||かんして|おり|ださ||じじつ||そうぞう||みょうな|はなし|||たん||ひやす|||
われわれ は 、 ねずみ や 油虫 を 食べて 生きて いる ので ない と して も 、 蓮 の 香 を 吸って 生きて いる と 思われて いる 。
||||あぶらむし||たべて|いきて|||||||はす||かおり||すって|いきて|||おもわ れて|
これ は 、 つまらない 狂信 か 、 さもなければ 見さげ 果てた 逸 楽である 。
|||きょうしん|||みさげ|はてた|そら|らくである
インド の 心 霊 性 を 無知 と いい 、 シナ の 謹 直 を 愚 鈍 と いい 、 日本 の 愛国 心 を ば 宿命 論 の 結果 と いって あざけられて いた 。
いんど||こころ|れい|せい||むち|||しな||つつし|なお||ぐ|どん|||にっぽん||あいこく|こころ|||しゅくめい|ろん||けっか|||あざけら れて|
はなはだしき は 、 われわれ は 神経 組織 が 無 感覚 なる ため 、 傷 や 痛み に 対して 感じ が 薄い と まで 言われて いた 。
||||しんけい|そしき||む|かんかく|||きず||いたみ||たいして|かんじ||うすい|||いわ れて|
西洋 の 諸君 、 われわれ を 種 に どんな こと でも 言って お 楽しみ なさい 。
せいよう||しょくん|||しゅ|||||いって||たのしみ|
アジア は 返礼 いたします 。
あじあ||へんれい|いたし ます
まだまだ おもしろい 種 に なる こと は いくら でも あろう 、 もし われわれ 諸君 に ついて これ まで 、 想像 したり 書いたり した こと が すっかり お わかり に なれば 。
||しゅ||||||||||しょくん|||||そうぞう||かいたり||||||||
すべて 遠き もの を ば 美し と 見 、 不思議に 対して 知らず知らず 感服 し 、 新しい 不 分 明 な もの に 対して は 、 口 に は 出さ ね ど 憤る と いう こと が そこ に 含まれて いる 。
|とおき||||うつくし||み|ふしぎに|たいして|しらずしらず|かんぷく||あたらしい|ふ|ぶん|あき||||たいして||くち|||ださ|||いきどおる|||||||ふくま れて|
諸君 は これ まで 、 うらやましく 思う こと も でき ない ほど 立派な 徳 を 負わされて 、 あまり 美しくて 、 とがめる こと の でき ない ような 罪 を きせられて いる 。
しょくん|||||おもう||||||りっぱな|とく||おわさ れて||うつくしくて|||||||ざい||きせ られて|
わが国 の 昔 の 文人 は ―― その 当時 の 物知り であった ―― まあ こんな こと を 言って いる 。
わがくに||むかし||ぶんじん|||とうじ||ものしり||||||いって|
諸君 に は 着物 の どこ か 見え ない ところ に 、 毛 深い しっぽ が あり 、 そして しばしば 赤ん坊 の 細切り 料理 を 食べて いる と !
しょくん|||きもの||||みえ||||け|ふかい||||||あかんぼう||こまぎり|りょうり||たべて||
否 、 われわれ は 諸君 に 対して もっと 悪い こと を 考えて いた 。
いな|||しょくん||たいして||わるい|||かんがえて|
すなわち 諸君 は 、 地球 上 で 最も 実行 不可能な 人種 と 思って いた 。
|しょくん||ちきゅう|うえ||もっとも|じっこう|ふかのうな|じんしゅ||おもって|
と いう わけ は 、 諸君 は 決して 実行 し ない こと を 口 で は 説いて いる と いわれて いた から 。
||||しょくん||けっして|じっこう|||||くち|||といて|||いわ れて||
かく の ごとき 誤解 は われわれ の うち から すみやかに 消え去って ゆく 。
|||ごかい|||||||きえさって|
商業 上 の 必要に 迫られて 欧州 の 国語 が 、 東洋 幾多 の 港 に 用いられる ように なって 来た 。
しょうぎょう|うえ||ひつように|せまら れて|おうしゅう||こくご||とうよう|いくた||こう||もちい られる|||きた
アジア の 青年 は 現代 的 教育 を 受ける ため に 、 西洋 の 大学 に 群がって ゆく 。
あじあ||せいねん||げんだい|てき|きょういく||うける|||せいよう||だいがく||むらがって|
われわれ の 洞察 力 は 、 諸君 の 文化 に 深く 入り込む こと は でき ない 。
||どうさつ|ちから||しょくん||ぶんか||ふかく|はいりこむ||||
しかし 少なくとも われわれ は 喜んで 学ぼう と して いる 。
|すくなくとも|||よろこんで|まなぼう|||
私 の 同国 人 の うち に は 、 諸君 の 習慣 や 礼儀 作法 を あまりに 多く 取り入れた 者 が ある 。
わたくし||どうこく|じん|||||しょくん||しゅうかん||れいぎ|さほう|||おおく|とりいれた|もの||
こういう 人 は 、 こわばった カラ や 丈 の 高い シルクハット を 得る こと が 、 諸君 の 文明 を 得る こと と 心得違い を して いた のである 。
|じん|||から||たけ||たかい|||える|||しょくん||ぶんめい||える|||こころえちがい||||
かかる 様子 ぶり は 、 実に 哀れむ べき 嘆かわしい もの である が 、 ひざまずいて 西洋 文明 に 近づこう と する 証拠 と なる 。
|ようす|||じつに|あわれむ||なげかわしい|||||せいよう|ぶんめい||ちかづこう|||しょうこ||
不幸に して 、 西洋 の 態度 は 東洋 を 理解 する に 都合 が 悪い 。
ふこうに||せいよう||たいど||とうよう||りかい|||つごう||わるい
キリスト教 の 宣教師 は 与える ため に 行き 、 受けよう と は し ない 。
きりすときょう||せんきょうし||あたえる|||いき|うけよう||||
諸君 の 知識 は 、 もし 通りすがり の 旅人 の あて に なら ない 話 に 基づく ので なければ 、 わが 文学 の 貧弱な 翻訳 に 基づいて いる 。
しょくん||ちしき|||とおりすがり||たびびと||||||はなし||もとづく||||ぶんがく||ひんじゃくな|ほんやく||もとづいて|
ラフカディオ ・ ハーン の 義 侠的 ペン 、 または 『 インド 生活 の 組織 [1]』 の 著者 の それ が 、 われわれ みずから の 感情 の 松明 を もって 東洋 の 闇 を 明るく する こと は まれである 。
|||ただし|きょうてき|ぺん||いんど|せいかつ||そしき||ちょしゃ|||||||かんじょう||たいまつ|||とうよう||やみ||あかるく||||
私 は こんなに あけすけに 言って 、 たぶん 茶道 に ついて の 私 自身 の 無知 を 表わす であろう 。
わたくし||||いって||さどう||||わたくし|じしん||むち||あらわす|
茶道 の 高 雅 な 精神 そのもの は 、 人 から 期待 せられて いる こと だけ 言う こと を 要求 する 。
さどう||たか|ただし||せいしん|その もの||じん||きたい|せら れて||||いう|||ようきゅう|
しかし 私 は 立派な 茶 人 の つもり で 書いて いる ので は ない 。
|わたくし||りっぱな|ちゃ|じん||||かいて||||
新旧 両 世界 の 誤解 に よって 、 すでに 非常な 禍 を こうむって いる のである から 、 お互い が よく 了解 する こと を 助ける ため に 、 いささか なり と も 貢献 する に 弁解 の 必要 は ない 。
しんきゅう|りょう|せかい||ごかい||||ひじょうな|か||||||おたがい|||りょうかい||||たすける|||||||こうけん|||べんかい||ひつよう||
二十 世紀 の 初め に 、 もし ロシア が へりくだって 日本 を よく 了解 して いたら 、 血なまぐさい 戦争 の 光景 は 見 ないで 済んだ であろう に 。
にじゅう|せいき||はじめ|||ろしあ|||にっぽん|||りょうかい|||ちなまぐさい|せんそう||こうけい||み||すんだ||
東洋 の 問題 を さげすんで 度外 視 すれば 、 なんという 恐ろしい 結果 が 人類 に 及ぶ こと であろう 。
とうよう||もんだい|||どがい|し|||おそろしい|けっか||じんるい||およぶ||
ヨーロッパ の 帝国 主義 は 、 黄 禍 の ばかげた 叫び を あげる こと を 恥じ ない が 、 アジア も また 、 白 禍 の 恐るべき を さとる に 至る かも しれ ない と いう こと は 、 わかり かねて いる 。
よーろっぱ||ていこく|しゅぎ||き|か|||さけび|||||はじ|||あじあ|||しろ|か||おそるべき||||いたる||||||||||
諸君 は われわれ を 「 あまり 茶 気 が あり 過ぎる 」 と 笑う かも しれ ない が 、 われわれ は また 西洋 の 諸君 に は 天性 「 茶 気 が ない 」 と 思う かも しれ ないで は ない か 。
しょくん|||||ちゃ|き|||すぎる||わらう||||||||せいよう||しょくん|||てんせい|ちゃ|き||||おもう||||||
東西 両 大陸 が 互いに 奇 警 な 批評 を 飛ばす こと は やめ に して 、 東西 互いに 得る 利益 に よって 、 よし 物 が わかって 来 ない と して も 、 お互いに やわらかい 気持ち に なろう で は ない か 。
とうざい|りょう|たいりく||たがいに|き|けい||ひひょう||とばす||||||とうざい|たがいに|える|りえき||||ぶつ|||らい|||||おたがいに||きもち||||||
お互いに 違った 方面 に 向かって 発展 して 来て いる が 、 しかし 互いに 長短 相 補わ ない 道理 は ない 。
おたがいに|ちがった|ほうめん||むかって|はってん||きて||||たがいに|ちょうたん|そう|おぎなわ||どうり||
諸君 は 心 の 落ちつき を 失って まで 膨張 発展 を 遂げた 。
しょくん||こころ||おちつき||うしなって||ぼうちょう|はってん||とげた
われわれ は 侵略 に 対して は 弱い 調和 を 創造 した 。
||しんりゃく||たいして||よわい|ちょうわ||そうぞう|
諸君 は 信ずる こと が できます か 、 東洋 は ある 点 で 西洋 に まさって いる と いう こと を !
しょくん||しんずる|||でき ます||とうよう|||てん||せいよう|||||||
不思議に も 人情 は 今 まで の ところ 茶碗 に 東西 相 合して いる 。
ふしぎに||にんじょう||いま||||ちゃわん||とうざい|そう|あわして|
茶道 は 世界 的に 重んぜられて いる 唯一 の アジア の 儀式 である 。
さどう||せかい|てきに|おもんぜ られて||ゆいいつ||あじあ||ぎしき|
白人 は わが 宗教 道徳 を 嘲笑 した 。
はくじん|||しゅうきょう|どうとく||ちょうしょう|
しかし この 褐色 飲料 は 躊躇 も なく 受け入れて しまった 。
||かっしょく|いんりょう||ちゅうちょ|||うけいれて|
午後 の 喫茶 は 、 今や 西洋 の 社会 に おける 重要な 役 を つとめて いる 。
ごご||きっさ||いまや|せいよう||しゃかい|||じゅうような|やく|||
盆 や 茶托 の 打ち合う 微妙な 音 に も 、 ねんごろに もてなす 婦人 の 柔らかい 絹 ずれ の 音 に も 、 また 、 クリーム や 砂糖 を 勧められたり 断わったり する 普通の 問答 に も 、 茶 の 崇拝 は 疑い も なく 確立 して いる と いう こと が わかる 。
ぼん||ちゃたく||うちあう|びみょうな|おと|||||ふじん||やわらかい|きぬ|||おと||||くりーむ||さとう||すすめ られたり|ことわったり||ふつうの|もんどう|||ちゃ||すうはい||うたがい|||かくりつ|||||||
渋い か 甘い か 疑わしい 煎 茶 の 味 は 、 客 を 待つ 運命 に 任せて あきらめる 。
しぶい||あまい||うたがわしい|い|ちゃ||あじ||きゃく||まつ|うんめい||まかせて|
この 一事 に も 東洋 精神 が 強く 現われて いる と いう こと が わかる 。
|いちじ|||とうよう|せいしん||つよく|あらわれて||||||
ヨーロッパ に おける 茶 に ついて の 最も 古い 記事 は 、 アラビヤ の 旅行 者 の 物語 に ある と 言われて いて 、 八七九 年 以後 広東 に おける 主要なる 歳入 の 財源 は 塩 と 茶 の 税 であった と 述べて ある 。
よーろっぱ|||ちゃ||||もっとも|ふるい|きじ||||りょこう|もの||ものがたり||||いわ れて||はちしちきゅう|とし|いご|かんとん|||しゅようなる|さいにゅう||ざいげん||しお||ちゃ||ぜい|||のべて|
マルコポーロ は 、 シナ の 市 舶司 が 茶 税 を 勝手に 増した ため に 、 一二八五 年 免職 に なった こと を 記録 して いる 。
||しな||し|はくつかさ||ちゃ|ぜい||かってに|ました|||いちにはちご|とし|めんしょく|||||きろく||
ヨーロッパ 人 が 、 極東 に ついて いっそう 多く 知り 始めた の は 、 実に 大 発見 時代 の ころ である 。
よーろっぱ|じん||きょくとう||||おおく|しり|はじめた|||じつに|だい|はっけん|じだい|||
十六 世紀 の 終わり に オランダ 人 は 、 東洋 に おいて 灌木 の 葉 から さわやかな 飲料 が 造ら れる こと を 報じた 。
じゅうろく|せいき||おわり||おらんだ|じん||とうよう|||かんぼく||は|||いんりょう||つくら||||ほうじた
ジオヴァーニ ・ バティスタ ・ ラムージオ ( 一五五九 )、 エル ・ アルメイダ ( 一五七六 )、 マフェノ ( 一五八八 )、 タレイラ ( 一六一〇 ) ら の 旅行 者 たち も また 茶 の こと を 述べて いる [2]。
|||いちごごきゅう|||いちごしちろく||いちごはちはち||いちろくいち|||りょこう|もの||||ちゃ||||のべて|
一六一〇 年 に 、 オランダ 東 インド 会社 の 船 が ヨーロッパ に 初めて 茶 を 輸入 した 。
いちろくいち|とし||おらんだ|ひがし|いんど|かいしゃ||せん||よーろっぱ||はじめて|ちゃ||ゆにゅう|
一六三六 年 に は フランス に 伝わり 、 一六三八 年 に は ロシア に まで 達した 。
いちろくさんろく|とし|||ふらんす||つたわり|いちろくさんはち|とし|||ろしあ|||たっした
英国 は 一六五〇 年 これ を 喜び 迎えて 、「 か の 卓 絶 せる 、 かつ すべて の 医者 の 推奨 する シナ 飲料 、 シナ 人 は これ を チャ と 呼び 、 他 国民 は これ を テイ または ティー と 呼ぶ 。」
えいこく||いちろくご|とし|||よろこび|むかえて|||すぐる|た|||||いしゃ||すいしょう||しな|いんりょう|しな|じん||||||よび|た|こくみん||||てい||||よぶ
と 言って いた 。
|いって|
この世 の すべて の よい 物 と 同じく 、 茶 の 普及 も また 反対に あった 。
このよ|||||ぶつ||おなじく|ちゃ||ふきゅう|||はんたいに|
ヘンリー ・ セイヴィル ( 一六七八 ) の ような 異端 者 は 、 茶 を 飲む こと を 不潔な 習慣 と して 口 を きわめて 非難 した 。
||いちろくしちはち|||いたん|もの||ちゃ||のむ|||ふけつな|しゅうかん|||くち|||ひなん|
ジョウナス ・ ハンウェイ は 言った 。
|||いった
( 茶 の 説 ・一七五六) 茶 を 用いれば 男 は 身のたけ 低く なり 、 み め を そこない 、 女 は その 美 を 失う と 。
ちゃ||せつ|いちしちごろく|ちゃ||もちいれば|おとこ||みのたけ|ひくく||||||おんな|||び||うしなう|
茶 の 価 の 高い ため に ( 一 ポンド 約 十五 シリング ) 初め は 一般 の 人 の 消費 を 許さ なかった 。
ちゃ||か||たかい|||ひと|ぽんど|やく|じゅうご||はじめ||いっぱん||じん||しょうひ||ゆるさ|
「 歓待 饗応 用 の 王室 御用 品 、 王侯 貴族 の 贈答 用品 」 と して 用いられた 。
かんたい|きょうおう|よう||おうしつ|ごよう|しな|おうこう|きぞく||ぞうとう|ようひん|||もちい られた
しかし こういう 不利な 立場 に ある に も かかわら ず 、 喫茶 は 、 すばらしい 勢い で 広まって 行った 。
||ふりな|たちば|||||||きっさ|||いきおい||ひろまって|おこなった
十八 世紀 前半 に おける ロンドン の コーヒー 店 は 、 実際 喫茶 店 と なり 、 アディソン や スティール の ような 文士 の つどう ところ と なり 、 茶 を 喫し ながら かれら は 退屈しのぎ を した もの である 。
じゅうはち|せいき|ぜんはん|||ろんどん||こーひー|てん||じっさい|きっさ|てん||||||||ぶんし||||||ちゃ||きっし||||たいくつしのぎ||||
この 飲料 は まもなく 生活 の 必要 品 ―― 課税 品 ―― と なった 。
|いんりょう|||せいかつ||ひつよう|しな|かぜい|しな||
これ に 関連 して 、 現代 の 歴史 に おいて 茶 が いかに 主要な 役 を 務めて いる か を 思い出す 。
||かんれん||げんだい||れきし|||ちゃ|||しゅような|やく||つとめて||||おもいだす
アメリカ 植民 地 は 圧迫 を 甘んじて 受けて いた が 、 ついに 、 茶 の 重税 に 堪えかねて 人間 の 忍耐 力 も 尽きて しまった 。
あめりか|しょくみん|ち||あっぱく||あまんじて|うけて||||ちゃ||じゅうぜい||たえかねて|にんげん||にんたい|ちから||つきて|
アメリカ の 独立 は 、 ボストン 港 に 茶 箱 を 投じた こと に 始まる 。
あめりか||どくりつ||ぼすとん|こう||ちゃ|はこ||とうじた|||はじまる
茶 の 味 に は 微妙な 魅力 が あって 、 人 は これ に 引きつけられ ない わけに は ゆか ない 、 また これ を 理想 化 する ように なる 。
ちゃ||あじ|||びみょうな|みりょく|||じん||||ひきつけ られ|||||||||りそう|か|||
西洋 の 茶 人 たち は 、 茶 の かおり と かれら の 思想 の 芳香 を 混 ずる に 鈍 で は なかった 。
せいよう||ちゃ|じん|||ちゃ||||||しそう||ほうこう||こん|||どん|||
茶 に は 酒 の ような 傲慢な ところ が ない 。
ちゃ|||さけ|||ごうまんな|||
コーヒー の ような 自覚 も なければ 、 また ココア の ような 気取った 無邪気 も ない 。
こーひー|||じかく||||ここあ|||きどった|むじゃき||
一七一一 年 に すでに スペクテイター 紙 に 次 の ように 言って いる 。
いちしちいちいち|とし||||かみ||つぎ|||いって|
「 それゆえに 私 は 、 この 私 の 考え を 、 毎朝 、 茶 と バタ つき パン に 一 時間 を 取って おか れる ような 、 すべて の 立派な 御 家庭 へ 特に お 勧め したい と 思います 。
|わたくし|||わたくし||かんがえ||まいあさ|ちゃ||||ぱん||ひと|じかん||とって||||||りっぱな|ご|かてい||とくに||すすめ|し たい||おもい ます
そして 、 どうぞ この 新聞 を 、 お茶 の したく の 一部分 と して 、 時間 を 守って 出す ように お 命じ に なる こと を 、 せつに お 勧め いたします 。」
|||しんぶん||おちゃ||||いちぶぶん|||じかん||まもって|だす|||めいじ|||||||すすめ|いたし ます
サミュエル ・ ジョンソン は みずから の 人物 を 描いて 次 の ように 言って いる 。
|||||じんぶつ||えがいて|つぎ|||いって|
「 因 業 な 恥知らずの お茶 飲み で 、 二十 年間 も 食事 を 薄く する に ただ この 魔力 ある 植物 の 振り出し を もって した 。
いん|ぎょう||はじしらずの|おちゃ|のみ||にじゅう|ねんかん||しょくじ||うすく|||||まりょく||しょくぶつ||ふりだし|||
そして 茶 を もって 夕べ を 楽しみ 、 茶 を もって 真 夜中 を 慰め 、 茶 を もって 晨 を 迎えた 。」
|ちゃ|||ゆうべ||たのしみ|ちゃ|||まこと|よなか||なぐさめ|ちゃ|||しん||むかえた
ほんとうの 茶 人 チャールズ ・ ラム は 、「 ひそかに 善 を 行なって 偶然に これ が 現われる こと が 何より の 愉快である 。」
|ちゃ|じん|ちゃーるず||||ぜん||おこなって|ぐうぜんに|||あらわれる|||なにより||ゆかいである
と いう ところ に 茶道 の 真髄 を 伝えて いる 。
||||さどう||しんずい||つたえて|
と いう わけ は 、 茶道 は 美 を 見いださ ん が ため に 美 を 隠す 術 であり 、 現わす こと を はばかる ような もの を ほのめかす 術 である 。
||||さどう||び||みいださ|||||び||かくす|じゅつ||あらわす||||||||じゅつ|
この 道 は おのれ に 向かって 、 落ち着いて しかし 充分に 笑う けだかい 奥義 である 。
|どう||||むかって|おちついて||じゅうぶんに|わらう||おうぎ|
従って ヒューマー そのもの であり 、 悟り の 微笑 である 。
したがって||その もの||さとり||びしょう|
すべて 真に 茶 を 解する 人 は この 意味 に おいて 茶 人 と 言って も よかろう 。
|しんに|ちゃ||かいする|じん|||いみ|||ちゃ|じん||いって||
たとえば サッカレー 、 それ から シェイクスピア は もちろん 、 文芸 廃 頽期 の 詩人 も また 、( と 言って も 、 いずれ の 時 か 廃 頽期 で なかろう ) 物質 主義 に 対する 反抗 の あまり いくらか 茶道 の 思想 を 受け入れた 。
||||しぇいくすぴあ|||ぶんげい|はい|たいき||しじん||||いって||||じ||はい|たいき|||ぶっしつ|しゅぎ||たいする|はんこう||||さどう||しそう||うけいれた
たぶん 今日 に おいて も この 「 不完全 」 を 真摯に 静観 して こそ 、 東西 相 会して 互いに 慰める こと が できる であろう 。
|きょう|||||ふかんぜん||しんしに|せいかん|||とうざい|そう|かいして|たがいに|なぐさめる||||
道 教徒 は いう 、「 無 始 」 の 始め に おいて 「 心 」 と 「 物 」 が 決死 の 争 闘 を した 。
どう|きょうと|||む|はじめ||はじめ|||こころ||ぶつ||けっし||あらそ|たたか||
ついに 大 日輪 黄 帝 は 闇 と 地 の 邪 神 祝 融 に 打ち勝った 。
|だい|にちりん|き|みかど||やみ||ち||じゃ|かみ|いわい|とおる||うちかった
その 巨人 は 死 苦 の あまり 頭 を 天 涯 に 打ちつけ 、 硬 玉 の 青天 を 粉砕 した 。
|きょじん||し|く|||あたま||てん|がい||うちつけ|かた|たま||せいてん||ふんさい|
星 は その 場所 を 失い 、 月 は 夜 の 寂 寞 たる 天空 を あて も なく さまよう た 。
ほし|||ばしょ||うしない|つき||よ||じゃく|ばく||てんくう||||||
失望 の あまり 黄 帝 は 、 遠く 広く 天 の 修理 者 を 求めた 。
しつぼう|||き|みかど||とおく|ひろく|てん||しゅうり|もの||もとめた
捜し 求めた かい は あって 東方 の 海 から 女 媧 と いう 女 皇 、 角 を いただき 竜 尾 を そなえ 、 火 の 甲 冑 を まとって 燦 然 たる 姿 で 現われた 。
さがし|もとめた||||とうほう||うみ||おんな||||おんな|こう|かど|||りゅう|お|||ひ||こう|ちゅう|||さん|ぜん||すがた||あらわれた
その 神 は 不思議な 大釜 に 五色 の 虹 を 焼き 出し 、 シナ の 天 を 建て直した 。
|かみ||ふしぎな|おおかま||ごしき||にじ||やき|だし|しな||てん||たてなおした
しかしながら 、 また 女 媧 は 蒼天 に ある 二 個 の 小 隙 を 埋める こと を 忘れた と 言われて いる 。
||おんな|||そうてん|||ふた|こ||しょう|すき||うずめる|||わすれた||いわ れて|
かく の ごとく して 愛 の 二元論 が 始まった 。
||||あい||にげんろん||はじまった
すなわち 二 個 の 霊 は 空間 を 流転 して とどまる こと を 知ら ず 、 ついに 合して 始めて 完全な 宇宙 を なす 。
|ふた|こ||れい||くうかん||るてん|||||しら|||あわして|はじめて|かんぜんな|うちゅう||
人 は おのおの 希望 と 平和 の 天空 を 新たに 建て直さ なければ なら ぬ 。
じん|||きぼう||へいわ||てんくう||あらたに|たてなおさ|||
現代 の 人道 の 天空 は 、 富 と 権力 を 得 ん と 争う 莫大な 努力 に よって 全く 粉砕 せられて いる 。
げんだい||じんどう||てんくう||とみ||けんりょく||とく|||あらそう|ばくだいな|どりょく|||まったく|ふんさい|せら れて|
世 は 利己 、 俗悪 の 闇 に 迷って いる 。
よ||りこ|ぞくあく||やみ||まよって|
知識 は 心 に やましい こと を して 得られ 、 仁 は 実利 の ため に 行なわれて いる 。
ちしき||こころ||||||え られ|しとし||じつり||||おこなわ れて|
東西 両 洋 は 、 立ち 騒ぐ 海 に 投げ入れられた 二 竜 の ごとく 、 人生 の 宝玉 を 得よう と すれ ど その かい も ない 。
とうざい|りょう|よう||たち|さわぐ|うみ||なげいれ られた|ふた|りゅう|||じんせい||ほうぎょく||えよう|||||||
この 大 荒廃 を 繕う ため に 再び 女 媧 を 必要 と する 。
|だい|こうはい||つくろう|||ふたたび|おんな|||ひつよう||
われわれ は 大権 化 の 出現 を 待つ 。
||たいけん|か||しゅつげん||まつ
まあ 、 茶 でも 一口 すすろう で は ない か 。
|ちゃ||ひとくち|||||
明るい 午後 の 日 は 竹林 に はえ 、 泉水 は うれし げ な 音 を たて 、 松 籟 は わが 茶釜 に 聞こえて いる 。
あかるい|ごご||ひ||たけばやし|||せんすい|||||おと|||まつ|らい|||ちゃがま||きこえて|
はかない こと を 夢 に 見て 、 美しい 取りとめ の ない こと を あれ や これ や と 考えよう で は ない か 。
|||ゆめ||みて|うつくしい|とりとめ||||||||||かんがえよう||||